この記事を読むのに必要な時間は推定で最大約3分48秒で、速読ですとその半分ぐらいです。
※2025-07-01時点で作成した記事ですので、奇跡が起これば状況が変わる可能性はあるかもしれません。
防衛装備の輸出実績はわずか1件だけ
2014年に「防衛装備移転三原則」が策定されて、防衛装備品の輸出が原則容認されるようになったわけなのですが、売れていません。
日本政府が防衛装備品の輸出を原則として認めてから10年以上がたった。その間、新品の完成品の輸出実績は1件しかない。日本の防衛産業も政府も長く輸出を禁止していた時代に根付いた特有の発想や商売手法があるからだ。世界基準からずれたままでは需要はあっても売れない状況は打開できない。
唯一売ることができたのは何だったのか。それは、三菱電機の警戒管制レーダーが2020年にフィリピンへの輸出契約が成立して、4基のレーダーが納入されたという案件だけ。奇跡です。
そもそも相手にされていないでしょ?
超高額なので競合他社の装備を選んだほうが数を揃えられる
商習慣以前の問題となるのは、日本だけでしか使用していない装備だということ。どのようなものでも量産効果が出れば安くなるわけですが、そもそも競合他社と比べるのが失礼なほどに生産数が少ないため、量産されていない日本の装備はあり得ないほどの高額。誰が買うんじゃって話。数はかなり重要な要素となり得ます。
実戦での運用実績が存在しないから避けられる
戦場での実績がないのですから、いざという時に蛮地で使ってみたら予想外の事態がたびたび発生して何の役にも立たない産廃だったという結末すらあり得る。実績がない=そういうこと。そのような装備を買いたいと思うような国はないでしょう。
すでに起こっている問題でわかりやすいのは、売り込もうと幻想を抱いている哨戒機のP-1ではないでしょうか。
検査院が要因の一つとしたのが機器の不具合だ。IHIが製造するエンジンは空気中の塩分が付着するなどして一部の素材に腐食が生じ、一定数が使用不能になっていた。任務中の情報収集で必要となる電子機器や反撃に使う武器にも不具合がみられた。
検査院はこれまでに蓄積した知見を設計に反映させることなどの検討を求めた。
もう一つの要因に交換部品の不足を挙げた。国際情勢の急変や半導体不足、人手不足などの影響で、部品の発注から納品までの期間が想定より長期化し、整備時に機体同士で部品を流用する「共食い」と呼ばれる状況がみられた。
平時での運用でも問題が起こるような、あまりにも低すぎる仕様でも通っちゃうような性能要求は嘲笑されそうなレベルなのでは?💦 もちろん補修用の交換部品なども量産されていないから高額だし必要な時に供給されるのか不明レベル。まわりに運用している国がなければ戦時では整備もままならない。導入しようっていうのは無理じゃね?💦
超高額なのに稼働率が低いというのを晒してしまったわけで、購入があるとしてもP-1は1~2機を研究用に買うわってレベルのお付き合い程度だと予想してしまう。それが日本国内では大本営発表的に誇大化されそうなところまで見えるかもしれない。

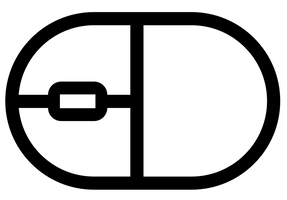

コメント